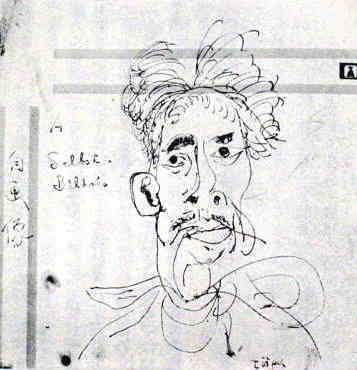洲之内徹の眼

【吉川孝昭のギャラリー】
洲之内徹の眼

| NO,4 渇き、求め続けた「卒直な魂」の存在。 |
青春期のころから波乱万丈の人生を送ってきた洲之内徹さんにとってシンプルで強靭な生命、迷いのない無垢な精神を垣間見ることは
なにものにも変えがたい体験で、それらの感覚との出会いのためだけに現代画廊で画商を続け、「気まぐれ美術館」の連載を続けてきた
といっても言い過ぎではないだろう。実にいろいろな画家が文章の中に登場するが、洲之内徹さんが生涯追い求めた「正直で卒直な精神」の
核にいたのが「小野幸吉」だったのではないだろうか。
洲之内さんは小野幸吉のことを「気まぐれ美術館」の中の『小野幸吉と高間筆子』、「帰りたい風景」の中の『海辺の墓』
『続 海辺の墓』、「さらば気まぐれ美術館」の中の『雪の降り方』と、実にたくさん書いている。
そしてそこにはいつものようなまわりくどさがなくこれも佐藤哲三の時と同様に直球勝負をしている。
彼はこの中で小野幸吉の絵を「渇きを癒してくれる絵」「生き返ったような気持ちになれる絵」と繰り返し言い切る。
小野幸吉の絵に洲之内さんが死んでも離したくない「なにものか」が存在するのは間違いない。
彼は仕事がらしょっちゅういろんな展覧会を見に行くがその度にとても辛い淋しい思いになるそうだ。そのことを
「大きな声を出した方が勝ち、というような絵がずらりとならんでいる。この居心地の悪さ。どちらを向いても私は生きた心地がしない。
どこにもこの身を托することのできるリアリティーがない。」と書く。
「うんざりするほど絵を見てきたばかりだというのに、却って、絵を見たいという激しい渇きのようなものに襲われる。絵とはあんな
ものじゃない。あんなものじゃないと思う。」とも書いている。
そして現代の世の中でやはり人々はもうリアリティを必要としていないことを悟り、「生きた心地がしない」と悲鳴をあげているのである。
そのような時、必ず彼は小野幸吉の、無垢な精神から産み落とされた数々の絵を思い出す。そして彼の絵を酒田で見た後、東京に帰っ
たとき、あの「渇き」がとまり、「絵に対する信頼感」が自分の裡(うち)に甦っているのだと書く。
小野幸吉は昭和5年に20歳の若さでこの世を去った山形県酒田生まれの異色の画家だ。洲之内さんは彼の芸術の背景にあった
今ではもうありえない『その時代』のことを「帰りたい風景」の中でこう書く。
「小野幸吉は20歳で死んでいる。正確には20歳と10ヶ月で死んだのだ。
そう聞くと、誰でも驚いてしまう。そして、誰もが彼の才能のことを言い、彼の生涯のあまりに早かった幕切れを惜しみ、この人が
もっと生きていたらどんな仕事をしたろう言う。また、小野の作品を見て、絵を描くことの原点のようなものをあらためて思い知らされた
という人がある。頭をぶん殴られたようだと言う人もある。ことごとく私は同感だし、みんなの言うことはよくわかるが、わかりながら、
いまはこんなふうに絵を描くことは出来ないのではないかという気が、私はだんだんとしてきたのだった。才能だけの問題ではない。
時代という言葉はなるべく使いたくないが、時代が違うのだ。こんなふうにひたすらに、まるで信仰のように、一切を自分の中に投入
して生きるということが、いまはできない。なぜだろう。いまは、見るものも知るものもあまりにも多すぎる。いわゆる情報過多というや
つで、若い人が絵を描く時でも、初めからあっちを見たりこっちを見たり、眼が外の方ばかり向いていて、自分を見失ってしまう。
万事世間様相手であるが、その世間の方が大衆社会というのか、中間社会というのか、仕合せとか幸福とかいう言葉がやたらに
流行する。こんな社会に、はたして芸術など必要だろうか。民主主義は芸術の敵だ。と、私はよく暴言を吐いていつも怒られるが、
すくなくとも、民主主義的嗜好に侵食されてしまった人間と社会からは、もはや芸術も芸術家も生まれないのではないのではないか、
という気が私はする。」
小野幸吉の絵と感覚、その生きざまが、洲之内さんがいうように現代ではもうありえないのだとしたら、その絵が、その感覚が好きでたま
らない洲之内さんはこの現代社会のなかで自分のこころの置き所を見つけることがはたしてできたのだろうか。
そして、また、小野幸吉のあの強烈な絵の背後にある独特なその時代だから許された制作態度についても彼は興味を強く持って私達に
知らせてくれる。
「小野幸吉は中学を3年でやめ、その秋東京へ出るがその時それまでの作品を火をつけて焼いてしまったということで、たまたま焼き忘れ
ていて残ったスケッチブックの中に1枚、墓の絵があるのだ。写生でないことのはっきりしている即興のいたずら描きのようなもので、
戒名も書きこまれたりして、どうやらそれは彼自身のことらしい。15歳の彼が自分の墓を描いているのである。彼のように、まるで絵をかき
に生まれてきたように絵を描いて描いて、しかも20歳でしんでしまうというような人間は、もしかすると自分の早世を予感しているのではな
いかという気がどうしてもする。彼の画集の中の、里見勝蔵氏の追悼文中の言い方を借りて言えば、まるで死に急いでいるような彼の絵の
描きぶりは、死に急ぐというよりも、死に追い迫られて、死と競争しているように見えないこともない。
彼の中学校時代というのが既に尋常でない。中学校に入ると同時に絵をかきはじめるが、毎日絵ばっかりかいていて、雨でも降らなければ
学校に出てこない。天気のよい日は、教室にはとてもじっとしていられなくて、何時間目だろうと構わず教室から姿を消してしまい、ついに
先生たちも彼のことを「お客様」と呼んで特別扱いした。と幼なじみの佐藤三郎氏が思い出の中に書いている。」
「…また別の友人の思い出だと、小野幸吉はその友人のところで高間筆子の画集を見つけると、自分に貸せといって持って行ってしまい、
絵を描きながら傍に置いて、『絵が出て来ない』とエメラルドやバーミリオンに汚れたままの手でその画集の貢をめくるので、画集を絵具だら
けにしてしまったということだ。(高間筆子は、たった2年間の制作活動のあと23歳の若さで自宅の2階から身を投げて死ぬ)」
こうして読んでいくと洲之内さんを「生き返ったようにしてくれた」のはまさしく小野幸吉の絵から匂い立つ「正直な卒直さ」であり、かつて人間が
卒直であることが出来た時代というものがこの国にはあったのだ。という深い感慨なのだろう。
そして彼はこう書く。
「卒直ということは美しい。いまの世の中にないのはそれなのだ。」と。
「…しかしいいも悪いもない。私は小野幸吉に感動した。私は小野幸吉が好きなのだ。」と。
洲之内さんが追い求めた「正直で卒直な魂と、芸術と人生への無垢な信仰」はいまのこの国の絵には見られない。そういうものをこの国も時
代も必要としていないことは誰でもわかる。そんな重くてしんどいものを背負ってはこのあまりにも複雑で無意味に忙しい今の世間の中では
誰もが身動きできなくなってしまうからであろう。
しかし、それならば、私は自分の人生をシンプルに、そして出来る限り忙しくなく送ろうと思う。そして何とか10年以上そのようにして生き
てきた。これからも死ぬまでそうしたい。そのような生き方に価値があるかどうかは知らないし、価値なんて私にはどうでもいいことだ。
そういうシンプルで無垢な精神が好きなだけだ。これは善悪や価値の問題ではなく、そうしたいと願い実践する、趣味の問題だと思う。
人は絵で人生を表現するのではなく、ただただ、絵を描くのだと思う。絵を描くというのは絵を描く以外の意味をもつ必要はなく、それ自体
で完結している。古今東西の本当の名作は皆この卒直さと強靭さのもとにのみあり、とてもシンプルだ。ちょっとがんばっただけの二流の
絵たちは余計な雑音を絵から発している。
そういう意味で私も洲之内さんと同じようにあの簡潔で強靭なそして何よりも卒直な小野幸吉の絵に強く惹かれる。
最後に「小野幸吉画集」に彼との思い出を載せた画家の大野五郎氏の文章の一部を紹介する。小野幸吉に対する気持ちが美しい。
「…それから、是非俺の仕事を見てくれと言って、無理に彼の部屋(その頃東中野の寒々しい下宿にいた)に私を連れて行った。
電車に乗ってからの小野はまったく黙ってしまって、いかにも後悔しているように見えた。私にはその気持ちがわかった。
狭い四畳半で不味いお茶を出した。彼は何枚か自分の絵を示して批評しろと責めた。
あまりに美しい、強烈な小野の色彩に驚いて、私はなんにも言わないでいた。彼は不平そうな顔つきで、『こんな絵っぴら』とかなんとか、ぶり
ぶり呟きながら引っ込めてしまった。彼の顔はだんだん蒼ざめてきた。「もう君帰ってくれないか」と、突然せわしく言い出して、鼻の先に手をあげ
たら、真っ赤な血が紺の服にどくどく流れ落ちた。私は不愉快な気持ちで雨の中を帰った。
私は彼が好きになった。それから4年友情を熱くしてきた。一緒に酒を飲んだ。喧嘩もした。街から街へと夜遅くまでふらついたことも度々だった。
彼の故郷に旅行した夏の記憶も、今となれば楽しく悲しい。彼は女に向かってはかなり乱暴な親切さを持っていた。よく狂った声をあげて人を
驚かした。彼は詩人だった。
懐かしいものだ。思い出すことは沢山あるが私には何も書けない。小野も画が描けないで淋しかろう。」
現存する小野幸吉の絵は現在大部分が酒田市の「本間美術館」に納められている。当時の本間美術館の副館長だった佐藤三郎氏が小野の
実家の酒蔵で黴臭くなって残されていた絵たちを美術館に運びこんで収蔵してくださったのだ。あの酒田市の大火があったのはそのたった数年
後で、小野幸吉の実家も全焼したらしい。佐藤三郎氏のおかげで現在私達は小野幸吉の絵を見ることが出来る。画集を再度刊行したのも
佐藤氏だと聞く。この方がいなければ小野幸吉の絵も記憶もこの世から消えていったことだろう。立派な方だと思う。
2003年2月11日
(小野幸吉 ランプのある静物A 油彩 1929年) (小野幸吉 自画像 油彩 1929年)


(小野幸吉 駅頭 油彩 1929年)

| NO,3 風景の深みへ徹る画家の眼。 |
洲之内徹の画家論を読んでいると、本当に彼が気に入っている作家が時々出てくる。そしてその作家の「この作品!」というところまで
つっこんで書いている場合もある。そういう時の洲之内さんが私は一番好きだ。一気に読めてしまう。よほど書きたいことがはっきりしている
のだろう。押さえ気味な表現ながら、その画家、その作品に向かう気迫があり、人生に立ち向かう姿が行間から立ち昇ってくる。
「絵のなかの散歩」にでてくる佐藤哲三についての文章もいつにもなく筆圧が強く、思い入れがある。
若くしてみずみずしい表現主義的な絵で華々しくデビューした佐藤哲三は、その後、政治的な農民運動の方へそれ、長い空白の日々があり、
その後、もう一度絵を再起させる時が来る。絵の天分を持った人間が、社会科学思考の世界から現実の世界へ立ち戻ったそのときを
こう書いている。
「佐藤哲三が再び、真に佐藤哲三として立ち現れるのは、そのあくる年、昭和24年の2月に描いた「寒い日」からである。4号の小品だが
まるで見ちがえるようだ。そして、立ち直ったというだけでなく、彼の晩年のいい作品の中だけに見られる、画家の眼が風景の深みへ
徹(とお)って、風景の魂に挑んでいるような鋭い気合、同時に、風景がすでに外界ではなくて作者の内部であるような一種の感覚が、この
作品で現れてくる。… この人の眼は社会科学入門的思考に煩わされないときには、こんなによく見えるのである。佐藤もまた、何の成心も
なくこの絵をかいたのにちがいない。この絵はあらかじめこういう絵をかこうとしてかいた絵ではなく、描き終わって筆を擱(お)いてみたらいい
絵ができていたという、そういう絵だと思うのであるが、画家にとって、それは至福の瞬間であろう。」
しかし佐藤哲三はこのときすでに健康を失っていた。長い農村実践運動の過労が原因だった。彼に最後の日が近づいてくるが彼の意識
は覚醒していく。洲之内さんはそのクライマックスをこう書く。
「昭和27年が終わり近くになり、蒲原平野に霙(みぞれ)が降りだす11月になって、佐藤哲三はあたらしく、意欲的な作品にとりかかる。
それが「みぞれ」である。毎日、きまって夕暮どきになると筆を採ったということだが、霙の季節と、夕暮れどきの感情とを、そのまま画面
に封じ込め、定着させようとしたのだったのかもしれない。霙は彼を生んだ北方の風土のひとつの象徴であり、霙降る薄暮に感じる想いは、
北国のひとびとだけが知る切実な感情であろう。こうして「みぞれ」はもはや彼一人の心象風景というようなところを超えて、彼の生まれた
北方の自然と、そこに生きる人々の心に深く係わりあうものになっている。だが、それにしても、彼はこの残照が赤々と空際を染める黄昏
の野を描くことで、図らずも、彼に迫っている彼自身の終末を描いたことに、自分で気がついていただろうか。 ともあれ「みぞれ」が彼の
生涯の最高の作品であることを私は疑わない。彼が北浦原の風土に深く沈潜することなしには、この作品が生まれなかったことも勿論
である。佐藤が農村に住んだことの意義が、ここへ来てはじめて明らかになってくる。」
洲之内さんにしてはめずらしく直線的にいいたいことを書いている。あの佐藤哲三の「みぞれ」と洲之内さん自身の原風景(中国大陸か)
がシンクロしていたのだろう。また、それと同時に佐藤哲三の思想的な挫折と再生を、そのまま過去の洲之内さんの青春期の挫折と再生に
繋げても考えていたことは容易に想像できる。
それでもなお、洲之内さんが感動したのはやはり「みぞれ」という絵そのものであって、やはりはじめに絵があるのであり、絵はいつの時代も
「匿名」なのである。
私も、佐藤哲三の絵は複製ではあるがたくさん見ている。初期の「赤帽平山氏」などの何枚かの傑作以上に晩年の「みぞれ」がいちばん画
家の体液が画面に溢れている、と思う。佐藤の一生一作だと思う。何年ものあいだ、生活の中でしだいに血肉になっていった原風景ともいえ
るその土と冷たい空気を、奇をてらわずにひたすら全身で感じ、その感覚だけを手がかりに画面に描き入れていった。そういう絵だ。無駄な
タッチはどこにも見当たらない。いつかぜひ本物を見たい。
そういえばヴィンセント.ヴァン.ゴッホが、サンレミやオーヴェールの風の中で絶望を隣に置いて描いた何枚かもまたそういう絵だったことを
思えば、本物の絵が生まれる条件の厳しさと、その感動を、今更ながら思い知らされる。しかし後世の評論家たちがどう彼らを哀れもうが、絵
を描いていた時の彼らの「至福の瞬間」は彼らだけのものだ。このことを信じられないで絵は描けない。洲之内さんは彼らの至福を肌で感じる
ことができる稀有な評論家だったと思う。
ちなみに洲之内さんは絵を描く。とてもいい絵だ。絵心を持った評論家だった。
2002年10月25日
(佐藤哲三作 「みぞれ」 1952年〜53年 油彩 60,5×133,0)

(洲之内徹さんの木版画。4枚とも。上手いのはもちろんのこと、絵心が溢れている。彼の画業はもっと認められてもよいと切に思う。)




| NO,2 「その事実」にたじろがぬ勇気。 |
洲之内徹にとって「絵を描くこと」とはどのようなことであったのか。「気まぐれ美術館」の、杉本鷹さんのことについて書かれた文章から
紹介してみる。
杉本さんは、持病の脊椎カリエスの身を押しながら高田馬場の自宅を改造して仲間と一緒に裸婦を描く研究所にし、56歳で亡くなる日
まで14年間、昼も、夜も研究生と一緒に裸婦を描き続けた人である。今のよくある「研究所」とは違い、画家と研究生との間に信頼と
連帯感があったと洲之内さんは書く。営利事業ではなく、受験の予備校でもなく、ただ絵を描きたい一心の連中の、熱気を帯びた寄り合い
であったそうだ。当時を知っている人は一様に「ああいう研究所はいまはもうないねえ。」というらしい。絵を描くということはどういうことか、
ということが、研究所全体の空気の中に、そして、杉本さんの日常の中にあった。洲之内さんはそんな杉本さんのことをこう書く。
『研究所での杉本さんについて、杉本鷹作品集の巻末で麻生三郎氏が、「彼は絵画が生活と離れるとだめになる原理を知っていたし、
そのことを若い人にじかに身につけることを指導していたようであった。」と書いている。 その若い連中にまじって、杉本さんは昼も夜も
絵を描き、そしてそうやって描いた何百枚の油絵の裸婦、何千枚のデッサンの裸婦が、誰に見せるでもなく、彼の死んだ後、彼の部屋に
積み上げられて残されていた。虚しいといえば恐ろしいほどの虚しさである。しかし、その一部が遺作展に並んだ時、それを見て「羨ましい」
と言った画家がある。何がその人を羨ましがらせたのか。芸術は本来無償の行為であるはずだが、杉本さんのように、その事実にたじろがぬ
勇気を持つことは、だれにでもできることではない。』そして杉本さんのスケッチブックの鉛筆スケッチを見て、『そのスケッチがみんないい。
見せようとして他人の目を意識することがないから、純粋で衒い(てらい)がなく、稀に見る美しさである。』と書いている。
小さな子供が無心に絵を描く行為と、絵描きが無心で絵を描く行為はどこかで繋がっていなければいけない。人は、絵「で」なにかを主張するの
ではなく、絵「を」描かねばならないのであろう。
そういえば小林秀雄が評論のなかでこのようなことを書いていた。 『 美しい花 、がある。 花の美しさ、というようなものはない。』
2002年7月20日
(杉本鷹 裸婦 油彩 )

| NO,1 「画家というもの」でない ― ということ。 |
洲之内徹さんが思う「良い絵」、とはいったいどのようなものであるかが分かりやすく文中に現れている代表的な例と
して「気まぐれ美術館」の土井虎賀壽氏のデッサンについて書かれた文章がある。土井さんは西洋哲学の研究者であり、絵も
描く。洲之内さんは、ニーチェの言った「画家というものは、結局は自分の気に入ったものを描く。そしてまた彼に描けるものはす
べて彼の気に入るのである。」という言葉に触発されて、土井さんのデッサンに思いを馳せていく。洲之内さんは次のように言っ
ている。
『私が考えるのはこういうことである。人はよく「絵になる」とか「絵にならない」とか言うが、それは、物を見て感動しても、自分に
それが描けるかどうか考えてみるのだということ、そのうちに追々自分の描けるものに自分の感動を限定するようになるかもしれ
ないということ、さらにまた、職業的な画家ともなればあおさら、自分の得意なものもの以外は対象を真剣に見ようとも、探そうとも
しなくなり、逆に、自分の身に付けた技術と様式に合わせてしか物を見なくなるのではないかということである。マンネリズムと
無感動の危険がそこに胚胎するが、「画家というもの」でない土井氏にはそれがない。感動があれば何にでも、顧慮することなく
氏の鉛筆はそのものに向かって行く。だから巧いデッサンも出来るが下手糞なデッサンも出来る。その代わり、巧くても下手でも
そのデッサンは生きていて、感動的なのだと…。』
「絵を描きたい」と最初に思った初々しい「絵心」の部分が「職業としての画家」に侵食されていくことが、しがらみだらけの社会の中で
いかに多いか、そしてその最初の「絵心」を持ち続けることこそが「絵を描く人」にとっては絶対条件だと洲之内さんは考えたのであ
ろう。絵には巧い絵は必要ないのだと、巧くても左脳的な硬直してしまっている絵は「死んでいる」ということであろう。逆にいえば、
線が生きているデッサンはそこに「感動」がある。だからそのような絵は下手な絵ではない。下手とか巧いではなく「いい絵」なのだと。
そして洲之内さんはそのような土井さんの行為は彼にとっての「救済」になっていると次のように言うのである。
『考えに耽りながら、土井さんはのろのろ歩く。道端にかやつり草の小さな花を見つけて、いつまでも立ち止まっている。スケッチブック
をひろげることもある。積もった落ち葉の中から色と形の美しい物を選んで、拾ってポケットに入れる。ポケットが枯葉でいっぱいになる。
あるときは舗装のアスファルトの上に砕け散った車のヘッドライトの破片に、「美しい」と言って眺め入り、やがてそこへかがみ込んで、
その氷砂糖のような破片を、ひとつひとつハンカチの中へ拾い集めたりした。散歩しながらも、土井さんの思索は続いているだろう。
だが、野草の花に見とれたり、枯葉を拾ったりしているときの氏には、その連続した不断の緊張からの、束の間の息抜きがあったので
はないだろうか。たぶんそれは、殆ど生理的な要請でもあったのだろう。氏にとって美は救済であったのだ。』
のっぴきならない人生の中で心を開放し、対象に感動し、「生理的」に絵を描く。すべての画家はこのことが自分の絵の出発点に今で
もあるのか、それとも、もうないのか、自分にもう一度真摯に問いただすことから始めるしかないのであろう。しかし、しがらみや高度
消費生活がもつれた糸のように絡み合ってしまった複雑な現代社会に生きている画家にとって、もう一度「画家というもの」でない、
「絵を描く人」に感覚を移せ、と言うことはとてつもなく酷なことかもしれないが、このことを抜きにして「再生」は絶対ないことも自明である。
2002年7月8日
(↓土井虎賀壽 自画像 スケッチ24×24)