偍婥妝僐儔儉
撔師榊側擔乆
僶僢僋僫儞僶乕俀侽侽俇擭俁寧暘
偦偺109乣偦偺131傑偱
傎傏枅擔峏怴
嵟怴偺僐儔儉偼偙偪傜
怴偟偄僶僢僋僫儞僶乕偼偙偪傜
僶儕搰丏媑愳岶徍偺僊儍儔儕乕撪丂
偍婥妝僐儔儉
撔師榊側擔乆
僶僢僋僫儞僶乕俀侽侽俇擭俁寧暘
偦偺109乣偦偺131傑偱
傎傏枅擔峏怴
嵟怴偺僐儔儉偼偙偪傜
怴偟偄僶僢僋僫儞僶乕偼偙偪傜
亀摨朎亁偺怺偄夰丂俁偮偺儔僗僩僔乕儞(2006,3,2係乯
挻儐僯乕僋側壨栰廏巕偝傫(2006,3,23)
朰傟傜傟側偄亀偰偮傗孨亁偺僄僺僜乕僪乮俀侽侽俇丆俁丆俀俀乯
庒嵷偝傫偺晭傟側偄栰媴僙儞僗乮俀侽侽俇丆俁丆俀侾乯
傆偠巕偝傫傕摨偠偔桬傒懌丠乮俀侽侽俇丆俁丆俀侽乯
憗昪偝傫偺桬傒懌乮俀侽侽俇丄俁丄侾俋乯
巹偺岲偒側億僗僞乕丏儀僗僩係乮俀侽侽俇丄俁丄侾俉乯
偡傑偗偄偝傫偺惷偐側惁傒乮俀侽侽俇丄俁丄侾俈乯
壛擺嶌師榊偺尵梩乮俀侽侽俇丄俁丄侾俇乯
傝偮巕偝傫偺僗儁僀儞梀妛偺嵿尮乮俀侽侽俇丄俁丄侾俆乯
偍偽偪傖傫偺巕庣塖乮俀侽侽俇丄俁丄侾係乯
嶰嵤拑榪偲僄儊儔儖僪偺巜椫乮俀侽侽俇丄俁丄侾俁乯
傆傒偝傫偺嵟屻偺椳乮俀侽侽俇丄俁丄侾俀乯
恴朘壠偲崟斅壠乮俀侽侽俇丄俁丄侾侾乯
媑揷擔弌巕偝傫偺巚偭偨偙偲乮俀侽侽俇丄俁丄10乯
惵弔婜偺亀抝偼偮傜偄傛亁乮俀侽侽俇丄俁丄俋乯
撔偲暫攏偺傗傝庢傝偺柇乮俀侽侽俇丄俁丄俉乯
岝巬偝傫偺婥帩偪偺亀傎傫偲偆亁乮俀侽侽俇丄俁丄俈乯
柉巕偺儈僯僊儍僌乮俀侽侽俇丄俁丄俇乯
埜揷偝傫偺懚嵼偺戝偒偝乮俀侽侽俇丄俁丄俆乯
亀梱偐側傞嶳偺屇傃惡亁偺媑壀廏棽偝傫乮俀侽侽俇丄俁丄係乯
亀屘嫿亁偺拞偺扟傛偟偺偝傫乮俀侽侽俇丄俁丄俁乯
扟傛偟偺偝傫偩偗偑弌偣傞亀埨傜偓亁乮俀侽侽俇丄俁丄俀乯
亀偨偩偠傖偡傑側偄抝亁偺僀儊乕僕乮俀侽侽俇丆俁丆侾乯
仛偙傟埲慜丄僶僢僋僫儞僶乕俀侽侽俇擭俀寧暘偼偙偪傜
仛偙傟埲慜丄僶僢僋僫儞僶乕俀侽侽俇擭侾寧暘偼偙偪傜
仛偙傟埲慜丄僶僢僋僫儞僶乕俀侽侽俆擭侾2寧暘偼偙偪傜
仛偙傟埲慜丄僶僢僋僫儞僶乕俀侽侽俆擭侾侾寧暘偼偙偪傜
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕 亀摨朎亁偺怺偄夰丂俁偮偺儔僗僩僔乕儞丂丂丂丂俁寧俀係擔乽撔師榊側擔乆乿偦偺侾俁侾 崱擔傕亀摨朎亁偱偄偒傑偟傚偆丅 徏旜懞偺惵擭夛庡嵜偺岞墘乽傆傞偝偲乿偼戝惉岟偵廔傢傝丄壨栰偝傫偼娾庤徏旜墂偱 棟帠夛偺庒幰偨偪偲嵟屻偺暿傟傪惿偟傓丅 斵彈偺僇僶儞偑傕偆偐側傝儓儗儓儗偵側偭偰偄偨偙偲傪抦偭偰偄偨斵傜偼崟帤偵側偭偨偺偱丄 偦偺拞偐傜壨栰偝傫偵怴偟偄僔儑儖僟乕僶僢僋傪僾儗僛儞僩偡傞丅 偦偟偰弌夛偄偺崰偺屗榝偄偲丄壗搙傕嵙愜偟偦偆偵側偭偨偙偲丄偦偟偰偦傟傪忔傝墇偊丄 寁夋傪棫偰丄弨旛傪偟丄偑傓偟傖傜偵側偭偰幚峴偟偨偙偲傪偍屳偄偵巚偄弌偟偰偟傑偄丄 壨栰偝傫傕斵傜傕栚傪弫傑偣偰偟傑偆丅惵弔偺壜擻惈偲偄偆偺偼偄偮傕堄奜惈偵枮偪偰偄傞丅 戝恖偨偪偑傢偗抦傝婄偱偁傜偐偠傔梊憐偡傞偙偲傛傝傕斵傜偼忢偵堦曕愭傪峴偔偺偩丅 壨栰偝傫偼尵偆 乽巹丄崱搙傕傑偨丄嫵偊傜傟偨傢丄傎傫偲偆偵偳偆傕偁傝偑偲偆乧乿 僇僙僢僩僥乕僾傪墴偟乽傆傞偝偲乿偑棳傟傞偲偄偆墘弌乮丱丱丟乯偵壨栰偝傫偼徫偄側偑傜傕悑偵 姶嬌傑偭偰偟傑偆丅 傒傫側偲埇庤偟丄尵梩傪岎傢偟側偑傜傕婦幵偼斵傜偐傜偳傫偳傫墦偞偐偭偰偄偔丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  偦偺偁偲丄斵彈偼惷偐偵嵗惾偵嵗偭偰姶奡偵傓偣傃媰偔偺偱偁傞丅 偁偁丄偄偄儔僗僩僔乕儞偩偲巚偭偰偄偨傜丄撍慠憢偺奜墦偔偱僋儔僋僔儑儞偺壒両 斵傜偺僕乕僾偑婦幵傪捛偭偰栆僗僺乕僪偱憱偭偰偔傞偱偼側偄偐丅忔偭偰偄傞偺偼 崅巙偲栁偲媏抮偩偭偨丅斵傜偼嫨傇乽偑傫偽傟乕両両乿 壨栰偝傫偼憢偐傜惛堦攖庤傪怳傝嫨傃偦偟偰椳偑傑偨棳傟傞丅 乽庤巻偪傚偆偩乧偄偹両乿 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  偁偁丄偙傟偱崱搙偙偦廔傢傝側傫偩偲丄尒偰偄傞偙偪傜傕嫻偑擬偔側偭偰偄傞偲丄崱搙偼 3儠寧屻丄崅巙偺壨栰偝傫傊偺庤巻偑偁傝丄廐偺廂妌帪偺墿嬥怓偵愼傑傞旤偟偄徏旜懞偑塮偭偰偄偔丅 偦偟偰丄偦偺捈屻丄塉忋偑傝偺杒奀摴偺梉挘偑塮傞丅崱擔丄壨栰偝傫偼扽峼偺挰梉挘偵偄傞偺偩丅 偙偺挰偺惵擭夛偺惵擭偲懪偪崌傢偣傪廔偊偰丄崱丄墂傊偺摴傪曕偄偰偄傞丅 偦偺摴偡偑傜斵彈偼偁偺徏旜懞偵弶傔偰拝偄偨偁偺擔偺傛偆偵乽傆傞偝偲乿傪岥偢偝傓丅 偦偺尐偵偼徏旜懞偺庒幰偨偪偐傜僾儗僛儞僩偝傟偨怴偟偄僔儑儖僟乕僶僢僋偑岝偭偰偄偨丅 斵彈偺屻巔偑彫偝偔側偭偰峴偒丄攝栶偑忋偐傜弌側偔嵍偐傜塃傊棳傟偰偄偔丅偙偺墶傊偺摦偒偼 偲偰傕怱抧傛偔丄埨掕偟偨梋塁偑偄偮傑偱傕巆傞棳傟偩偭偨丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 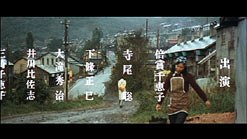 壨栰偝傫偼崱丄梉挘偺挰偺惵擭夛偺恖偨偪偲娭傢偭偰偄傞丅偁偺扽峼挿壆偼 乽岾暉偺墿怓偄僴儞僇僠乿偺桬嶌偲岝巬偝傫偺壠偺嬤偔偐傕偟傟側偄丅 乽岾暉偺墿怓偄僴儞僇僠乿偑惂嶌偝傟偨偺偼偦傟偐傜2擭屻偺偙偲偩丅 偲偙傠偱丄 嶳揷娔撀偼偙偺20擭屻偺1995擭偵徏旜懞偺偙偲傪憐偄丄偁傞尵梩傪斵傜偺偨傔偵婑偣偨偲尵偆丅 乽徏旜懞偺庒幰偨偪偲堦弿偵娋傪棳偟偰 塮夋乽摨朎乿傪嶌傝忋偘偨丂偁偺婸偐偟偄巚偄弌傪丄 杔偲杔偺僗僞僢僼偼堦惗朰傟側偄偩傠偆丅丂丂嶳揷梞師丂乿 巹偼傕偆堦搙尵偄偨偄丅 扤偑側傫偲尵偍偆偲巹偼偁偺塮夋偑岲偒偩丅 偁偺塮夋偺僗僢僞僢僼傗弌墘幰偺曽偨偪偲摨帪戙偵惗偒傞帠偑偱偒偨偟偁傢偣傪崱擔傕偐傒掲傔偰偄傞丅 柧擔偐傜僞僀偺僶儞僐僋偵弌挘偟傑偡丅僶儕偵栠偭偰偔傞偺偼1廡娫屻偺4寧2擔偱偡丅 偦傟備偊3寧25擔偐傜4寧1擔傑偱偼乽撔師榊偺擔乆乿偼偍媥傒偱偡丅屼椆彸偔偩偝偄丅
|
亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 挻儐僯乕僋側壨栰廏巕偝傫丂丂丂丂俁寧俀俁擔乽撔師榊側擔乆乿偦偺侾俁侽
|
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕 朰傟傜傟側偄亀偰偮傗孨亁偺僄僺僜乕僪丂丂丂丂俁寧俀俀擔乽撔師榊側擔乆乿偦偺侾俀俋
|
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕 庒嵷偝傫偺晭傟側偄栰媴僙儞僗丂丂丂丂俁寧俀侾擔乽撔師榊側擔乆乿偦偺侾俀俉
|
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕 傆偠巕偝傫傕摨偠偔桬傒懌丠丂丂丂丂俁寧侾俋擔乽撔師榊側擔乆乿偦偺侾俀俈 杺惈偺彈惈戝尨楉巕偝傫偑丄偦偺旤偟偝偵杹偒傪偐偗偰嵞搊応偟偨偺偑 戞34嶌乽撔師榊恀幚堦楬乿偱偁傞丅 偙偺帪傕側傫偲斵彈偼恖嵢偺栶丅傕偪傠傫偙偺帪偼偝偡偑偵棧崶偼偟側偄丅 偟偐偟丄晇偑幐鏗偟偰偟傑偆偺偱偁傞丅 傆偠巕偝傫偼丄偄傠偄傠晇偲墢偑偁偭偨撔偲擇恖偱晇傪幁帣搰傑偱扵偟偵峴偔偺偩偑丄 晇偑幐鏗偟偰柵擖偭偰偄傞斵彈傪撔偑偢偭偲椼傑偟丄堅傔傞懕偗傞偺偱偁傞丅 傕偪傠傫怱偺拞偱偼恖嵢偺傆偠巕偝傫傪垽偟偰偟傑偭偰偄傞帺暘偑偄傞傢偗偩丅 偦偟偰幐鏗偟偨晇偑巰偸偙偲傪峫偊偰偟傑偆嫲傠偟偄帺暘偲摤偆丄偲偄偆僔儕傾僗側暔岅偩丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  偨偩偟丄傆偠巕偝傫傕丄晇偑偄傞偲偄偆偺偵撔偵崨傟偰偟傑偭偰乧丄偲偄偆 偙偲偱偼側偔丄傂偨偡傜撔傪晇偺桭恖丄帺暘偨偪偺壎恖偲偟偰峫偊偰偄傞偺偩偑丄 幁帣搰偺廻偱丄曄側塡偑棫偨側偄傛偆偵偡偖偵傆偠巕偝傫偺晹壆偐傜弌偰僞僋僔乕偺 塣揮庤偺壠偵峴偙偆偲偡傞撔傪丄乽傕偆堦晹壆庢傟偽偄偄偠傖側偄乿偲丄堷偒偲傔傞僔乕儞偑 偁傞丅 偦偺帪傆偠巕偝傫偼乽偮傑傫側偄撔偝傫乧乿偲尵偆偺偱偁傞丅 偙傟偼偳偆偄偆堄枴偩傠偆偐丅 垽偡傞晇偑幐鏗偟丄懅巕傪壠偵巆偟偰丄敿媰偒偱撔偲堦弿偵扵偟夞偭偰偄傞嵟拞側傫偩偐傜丄 偁傞堄枴丄乽偮傑傫側偄乿偺偼摉偨傝慜偱丄偦傫側偙偲傪傢偞傢偞拞擭撈恎抝惈偵尵偆偙偲偼 忬嫷偐傜峫偊偰晄壜巚媍偩偲尵傢偞傞傪摼側偄丅曄側岆夝傪偝傟傞応崌傕偁傞丅 暔岅傪亀偪傚偭偲婋偆偄姶偠偵偟偨偄亁偲偄偆墘弌偐傕偟傟側偄偑丄偙傟偱偼傆偠巕偝傫偺恖奿偑 媈傢傟傞偟丄斵彈偺愗幚偝傗斶偟傒偲偺僶儔儞僗傕庢傟側偄丅 戝尨楉巕偝傫偵偁偁偄偆敪尵傪偝偣偰傒偨偄丄偲偄偆梸媮偼偲偰傕捝偄傎偳暘偐傞偑乮丱丱丟乯乁 偙偙偼丄偖偭乣乣偭偲丄偦偺梸媮傪姮偊偰丄 乽偳偆偟偰乧丠偦傫側墦椂偟側偔偨偭偰偄偄偺偵乧丄偱傕偁傝偑偲偆丄婥傪巊偭偰偔偩偝偭偰乧乿 偔傜偄偺偙偲傪旤偟偔墘弌偟偨傎偆偑傛偐偭偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  偙偙偼丄偁偔傑偱傕撔偑堦恖偱崨傟偰偟傑偭偰幍揮敧搢擸傔偽偄偄傢偗偱丄傆偠巕偝傫偼 枹偩斶偟傒偺拞偵杽杤偟偰偄傞偺偑帺慠偩側傫偰巚偆偺偼丄偪傚偭偲恀柺栚偡偓傞偱偟傚偆偐丅 傑偨柧擔
|
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕 憗昪偝傫偺桬傒懌丂丂丂丂俁寧侾俋擔乽撔師榊側擔乆乿偦偺侾俀俇 恖偼嬯偟偄帪斶偟偄帪偵懠恖偵堅傔傜傟傞偲丄傎傫偲偆偵婐偟偄傕偺偩丅 僴僀價僗僇僗偺壴偺儕儕乕偑堦斣偄偄椺偩偑丄撔師榊柌枍偺偍愮戙偝傫傕 撔偺桪偟偝偵媰偄偰偟傑偭偨丅 偦偟偰戞俀俀嶌乽塡偺撔師榊乿偱棧崶傪偟偰偟傑偭偨憗昪偝傫傕撔偺桪偟偝偵媬傢傟傞 偺偱偁傞丅 撔偼側傫偲偐拑偺娫偱憗昪偝傫偺怱傪榓傑偦偆偲偡傞偺偩偑丄椺偺擛偔慡偰 棤栚偵弌傞丅 曮偔偠偵僪乕儞偲摉偨偭偨丄嬻偐傜堦枩墌嶥偑僸儔僸儔僸儔僸儔棊偪偰偒偨丄 丄棤掚傪偪傚偭偲孈偭偨傜彫敾偑僓僋僓僋弌偰偒偨偲丄傢偗偺傢偐傜側偄 椺偊傪偡傞撔丅 偍偽偪傖傫偼壓悈岺帠偱孈傝曉偟偰悈摴娗偵寠偁偗偰偖偪傖偖偪傖偵側偭偨榖丅 偦傟柧傞偔側偄偭偰乮丱丱丟乯 阨椯摪偵憃巕偑偱偒偨丅偲偣偭偐偔偝偔傜偑柧傞偄榖傪偟偨偺偵丄 僞僐幮挿偑丄亀棧崶亁偲偄偆尵梩傪弌偟偰偟傑偭偰杤丅乮丱丱丟乯 偦傟偱傕枮抝偑崙岅偱侾侽侽揰庢偭偨偭偰婌傫偱偄偨攷丅 撔濰偔乽攲晝偝傫偵帡偨傫偩側乿 偦偺捈屻偵棟壢偺俁侽揰偑僶儗偰丄攷搟傝怱摢丅丂 枮抝濰偔亀嶴傔乣亁 偍偄偪傖傫濰偔乽攲晝偝傫偵帡偨偐乿乮丱丱丟乯 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  偱丄憗昪偝傫帺傜庤傪忋偘偰 憗昪乽僴僀両柧傞偄榖戣乿 撔乽僴僀丄側傫偱偟傚偆乿 憗昪乽偁偺偹丄巹偺恖惗偱撔偝傫偵夛偭偨偭偰偙偲乿 堦摨僔乣乣乣儞 偙偙傑偱偼側傫偲偐傛偐偭偨偺偩偑丄 偦偺偁偲婣傝嵺偵丄撔偵偙偆尵偆偺偩丅 乽偁偨偟乧撔偝傫岲偒傛両乿 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  偝偔傜偺尵偆傛偆偵丄傛傎偳丄偙偺栭偺抍烺偑偆傟偟偐偭偨偺偩傠偆偑丄 偙偺敪尵偵偼媈栤偑巆傞丅 偩偄偨偄丄偄偔傜怱傪堅傔偰傕傜偭偨偲偼偄偊丄偙偺擔偼憗昪偝傫偑晇偲棧崶偟偨 偽偐傝側偺偩丅 偙傟偼娫堘偭偰傕乽垽偺崘敀乿偱偼側偄丅 偁偺戞侾係嶌乽撔師榊巕庣塖乿偱垽傪崘敀偡傞栱懢榊惵擭偺 偁偺楒怱偲偼堎幙偺傕偺偱偁傞丅 撔偼楊巐廫傪墇偊偰偄傞撈恎偺抝偱偁傞丅 亀撔偵岲堄傪帩偪偼偠傔偨亁偔傜偄偱偄偔傜婐偟偔偰傕偪傚偭偲尵偄偡偓偱偼側偄偐丄偲 巚偭偰偟傑偆偺偱偁傞丅傑偟偰傗偁偺杺惈偺戝尨楉巕偝傫偺偁偺栚偱尵傢傟傞偲丄 撔偱側偔偰傕岆夝傪偟偰偟傑偆乮丱丱丟乯 偙偺憗昪偝傫偺亀桬傒懌亁偑撔偺楒傪壛懍偝偣丄寢壥揑偵斶偟傑偣偰偟傑偆 偙偲偵傕宷偑偭偰偄偔偺偱偁傞丅 偟偐偟丄幚偼憗昪偝傫傕撔偺偙偲傪岲偒偵側傝偐偗偰偨偺偐傕偟傟側偄丅 偦偟偰偦偺怱傪帩偭偨傑傑暿傟偑棃傞偺偑偣傔偰傕偺媬偄偐偲傕巚偭偨丅 儔僗僩偱側偵偐尵偄偨偘偩偭偨憗昪丅 憗昪乽偁偨偟偹乧乿 撔乽柧擔暦偔傛丄憗偔峴偐側偄偲娫偵偁傢偹偊偧丄側乿 撔偼傗偭傁傝僇僢僐傛偔偰偦偟偰垼偟偄乧丅 偙偺暔岅偺幐楒偼亀摼楒揑幐楒亁偺榞偵擖傟偰傛偄偐傕偲巚偭偰偄傞丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  傑偨柧擔
|
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 巹偺岲偒側億僗僞乕丏儀僗僩係丂丂丂丂俁寧侾俉擔乽撔師榊側擔乆乿偦偺侾俀俆 僶儕搰偺巹偺晹壆偵偼戞7嶌乽暠摤曆乿偺億僗僞乕偑戝偒偔揬偭偰偁傞丅撔偝傫婰擮娰偵 攧偭偰偄傞傕偺偺拞偱岲偒側億僗僞乕傪慖傫偱壗枃偐僶儕偵帩偭偰偒偨偺偩丅 偙偺乽暠摤曆乿偺億僗僞乕偼48嶌昳偺拞偱傕嵟傕岲偒側億僗僞乕偺堦偮偩丅 撔偺惏傟傗偐側惓柺婄丄偝偔傜偺偄偄昞忣丄幘憱偡傞忲婥婡娭幵丅僆乕僜僪僢僋僗偱 晛曊揑側億僗僞乕偱偁傞丅 抝偼偮傜偄傛偺億僗僞乕偼丄傒側偝傫偛彸抦偺捠傝亀揇廘偄亁亀偳傫偔偝偄亁 側傫偠傖偙傝傖偭偰偄偆傛偆側曄側億僗僞乕傕帪乆偁傞乮丱丱丟乯 偟偐偟丄偦偺偄偐偵傕徏抾揑側偳傫偔偝偝傕幚偼丄巹偼偦傫側偵寵偄偱偼側偄丅 偁傟偼偁傟偱僄僉僝僠僢僋偱偁傞丅 寢峔僇僢僐偄偄偲昡敾偺乽偨偦偑傟惔暫塹乿乽塀偟寱婼偺捾乿偺億僗僞乕偼妋偐偵栚怴偟偝傪慱偄丄 偍嬥傕偐偗丄偦偟偰惉岟偟偰傕偄傞偑丄偙偺屻侾侽侽擭偺楌巎偵暥壔揑偵懴偊傜傟傞偺偼 堄奜偵傕乽戞7嶌暠摤曆乿偺僆乕僜僪僢僋僗側偳傫偔偝偄億僗僞乕偺曽偐傕偟傟側偄丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  乽暠摤曆乿埲奜偺億僗僞乕偱偼戞10嶌乽撔師榊柌枍乿偺億僗僞乕傕岲偒偩丅梉曢傟帪丄 偍愮戙偝傫偑戣宱帥嶳栧偱塉廻傝傪偡傞撔偵嶱傪帩偭偰棃偰偁偘傞僇僢僩偑側傫偲傕旤偟偄丅 戞11嶌乽撔師榊朰傟側憪乿偺億僗僞乕傕戝岲偒丅撔偺尐偵杍傪婑偣傞儕儕乕偺昞忣偑 幚偵偄偄偺偩丅億僗僞乕偵彂偄偰偁傞僙儕僼偑偙傟傑偨廰偄丅 亀傎傜丄埀偭偰偄傞帪偼側傫偲傕巚傢偹偊偗偳丄暿傟偨屻偱柇偵巚偄弌偡傂偲偑偄傑偡偹丅 乧偦偆偄偆彈偱偟偨傛丄偁傟偼亁 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 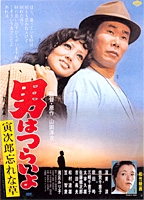 乽戞15嶌撔師榊憡崌偄嶱乿偺億僗僞乕傕丄撔偲儕儕乕偺昞忣偑惗偒惗偒偟偰抏偗偨姶偠偱偄偄丅 偙偺擇恖偑嵟傕恖惗偱壺傗偄偱偄偨帪婜偺徫婄偩丅 偙偺4偮偺億僗僞乕偑憤崌揑偵僟儞僩僣岲偒丅 億僗僞乕偺拞偺僙儕僼偩偗偱尵偆偲廰偄偺偼乽戞9嶌幠枖曠忣乿偺億僗僞乕偺僙儕僼 亀傎傜丄尒側傛丄偁偺塤偑桿偆偺傛丅 偨偩偦傟偩偗偺偙偲傛亁 偦傟偵偟偰傕偄偮傕巚偆偙偲偼丄億僗僞乕偺拞偺偝偔傜偺幨恀偼側偤偁偁傕壜垼憡側幨傝 側偺偩傠偆偐丅傑偭偨偔帡偰偄側偄幨傝偺婄偑懡偔丄偟偐傕摨偠幨恀傪壗搙傕巊傢傟偰偄偨傝偡傞丅 偝偔傜乣乮俿俿乯 傑偨柧擔 偙偺儁乕僕偺忋偵栠傞 嵟怴偺僐儔儉偼偙偪傜
|
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕丂 偡傑偗偄偝傫偺惷偐側惁傒丂丂丂丂俁寧侾俈擔乽撔師榊側擔乆乿偦偺侾俀係
|
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕 壛擺嶌師榊偺尵梩丂丂丂丂俁寧侾俇擔乽撔師榊側擔乆乿偦偺侾俀俁 戞俀俋嶌乽撔師榊偁偠偝偄偺楒乿偱搊応偡傞壛擺嶌師榊偼恖娫崙曮偵側偭偨崱偱傕丄偄偄拑榪偑 偱偒側偄偲擸傒丄擔乆惂嶌傪懹傜側偄丅 斵偺尵梩偵偙偆偄偆偺偑偁傞丅 乽搚偵怗偭偰傞偆偪偵帺慠偵宍偑惗傑傟偰偔傞傫傗丅 偙傫側宍偵偟傚偆偐偀丄偁傫側怓偵偟傚偆偐丄偰側偙偲丄偙傝傖摢偱峫偊偰傫偺偲偼堘偆傫傗丄 帺慠偵惗傑傟偰偔傞偺傪懸偮偺傗丅側丄偗偳乕丄偦偺帺慠偑側偐側偐擄偟偄乧乿 乽偁偺側丄偙傫側偊偊傕傫嶌傝偨偄偲偐偹丄恖偵朖傔傜傟傛偆偭偰偄偆傛偆側丄偁傎側偙偲峫偊偰傞偆偪偼丄 僼僢丄傠偔側傕傫偼偱偗傫傢乿 乽嶌傞偱側偄丅偙傟偼孈傝弌偡偹傗丅 偁乕丄搚偺拞偵旤偟偄乣乧傕傫偑偄偰側偁乧丄 弌偟偰偔傟偊乧丄偼傛弌偟偰偔傟偊偭偰乧媰偄偰傫偹傫乿 偙偺嶌師榊偺尵梩偼丄偦偺愄丄僀僞儕傾丏儖僱僢僒儞僗帪戙偵儈働儔儞僕僃儘偑尵偭偨尵梩偲帡偰偄傞丅 亀愇偺拞偵偁傞恄偺嶌傜傟偨憂憿暔傪帺暘偼僲儈傪巊偭偰挙傝弌偟偰偄傞偩偗偩亁偲丄尵偭偰偄偨偦偆偩丅 壛擺嶌師榊偺尵梩偺拞偱億僀儞僩偼乽偦偺帺慠偑側偐側偐擄偟偄乧乿偲偄偆偲偙傠丅 帺慠偵惗傑傟偰偔傞偲偄偆偙偲偼丄偨偩扨偵晛捠偺惗妶傪偟偰偄傟偽偄偄偲偄偆偙偲偱偼側偄丅 傗偼傝搚傪偄偠傝丄偙偹丄從偔丅偙偺孞傝曉偟傪尓嫊側怱傪帩偪側偑傜擔乆懕偗偰偄傞偲丄傆偲嬼慠丄 側偵偐偺僞僀儈儞僌偱丄枴傢偄怺偄偙偺悽偺傕偺偲偼巚偊側偄旤偟偄傕偺偑偱偒傞偙偲傕偁傞丅 偟偐偟丄嶌師榊傕惗恎偺恖娫丅偦偆偼尵偆傕偺偺丄梸傕偁傟偽丄偍嬥傕梸偟偄丅岥偱尵偭偰偄傞偙偲偲 幚嵺偺恖惗偼旝柇偵偢傟傞偺偱偁傞丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  偙偺柕弬傪撔偼柺敀偍偐偟偔朶偄偰偟傑偆丅 撔乽側偵傗偭偰栕偗偨偍偠偄偪傖傫丄偁乕偁乧丄拑榪從偄偨偩偗偱偙傟偩偗偺壠偼寶偨偹偊傕傫側偁丄 側偵偐堿偱偙偭偦傝埆偄偙偲偟偪傖偭偰乧丄傑偁偄偄傗丅偹丄偄傠偄傠偁傞偐傜側丄偍屳偄偵 尵偄偨偔偹偊偙偲偼丅僼僼乧乿 撔偑婣偭偨屻偱撈傝尵偺傛偆偵 嶌師榊乽僉僣僀偙偲尵偄傛傞乿 巹偑堦斣婥偵擖偭偰偄傞嶌師榊偺尵梩偑偁傞丅 撔偵帺暘偺乽怱帩偪乿偲偟偰婥偵擖偭偰偄傞乽懪栻梣曄嶰嵤榪乿傪偁偘傞偺偩偑丄 掜巕偑偦傟傪巭傔傛偆偲偟偨偲偒偺尵梩丄 乽偊偊偑側偊偊偑側乧偄偢傟偼妱傟傞傕傫傗丄從偒傕傫偼乿 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  斵偼帺暘偺怑嬈傪亀摡寍壠亁偲尵傢側偄偱亀從偒暔巘亁偲尵偆丅偄偄尵梩偩丅 傑偨柧擔 |
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕 傝偮巕偝傫偺僗儁僀儞梀妛偺嵿尮丂丂丂丂俁寧侾俆擔乽撔師榊側擔乆乿偦偺侾俀俀 巹偼挿偄娫奊傪昤偄偰丄攧偭偰惗妶傪偟偰偄傞偑丄 偙偺僔儕乕僘偱傕奊昤偒偝傫傗奊昤偒偝傫偺棏偑俁恖弌偰偔傞丅 戞侾俀嶌乽巹偺撔偝傫乿偺桍傝偮巕偝傫丄戞侾俈嶌乽撔師榊梉從偗彫從偗乿偺抮僲撪惵娤 戞俁俈嶌乽岾暉偺惵偄捁乿偺憅揷寬屷孨丄偱偁傞丅 傝偮巕偝傫偺敪尵乽傎傫偲偆偵帺暘偑婥偵擖偭偨嶌昳偲偄偆偺偼攧傝偨偔側偄丄 婥偵擖傜側偄嶌昳偼傑偡傑偡攧傝偨偔側偄乿偲偄偆婥帩偪偼丄暘偐傞側乣偦傟乧丄偩丅 奊偺偙偲偱擸傫偱偄傞斵傜偺巔傕丄暘偐傞暘偐傞丅摿偵寬屷孨偑嵥擻偺桳柍偱儎働偵 側偭偰偄傞僔乕儞側傫偐恎偵偮傑偝傟偰懠恖帠偱偼側偐偭偨丅 偲偙傠偱奊昤偒偲偄偆偺偼傑偢栕偐傜側偄丅帺怣傪帩偭偰偙傟偼尵偊傞 乮丱丱丟乯抮僲撪惵娤側傫偰偄偆偺偼丄傎傫偺堦埇傝偩丅巹傕傕偪傠傫側偐側偐攧傟側偄丅 奊偩偗偱偼姰慡偵偼惗妶偱偒側偄偺偱丄愼怐偺僨僓僀儞側偳偺撪怑傕偟偰偟偺偄偱偄傞丅 傝偮巕偝傫傕丄昻偟偐偭偨丅怘傋傞傕偺偵傕崲偭偰偄傞姶偠偩偭偨丅斵彈偑旤恖側偺偱 偔偭偮偄偰偔傞堦忦偲偄偆僗働儀側夋彜偑偄偨偑丄斵彈偼斵傪偲偰傕寵偑偭偰偄偨偺偱斵偵 奊傪戸偡偺傪柪偭偰偄傞傛偆偩偭偨丅 偁偺僔乕儞傪尒偰丄亀偦偺尐偵抲偄偨庤傪偺偗傠傛側堦忦乣両乮仴仴儊乯亁偭偰巚偭偰偄偨偺偼 巹偩偗偱偼偁傞傑偄乮丱丱丟乯 帪乆孼偺暥旻偑偍嬥傪悢枩墌抲偄偰偄偭偰偔傟傞偺偱丄側傫偲偐惗妶偑偱偒偰偄傞偲偄偆忬懺丅 撔偼丄傝偮巕偝傫傪椼傑偟丄僼儔儞僗僷儞乮僶働僢僩乯傪偍偛偭偰偁偘偨傝偟偰偄偨偺偱丄 乽撔偝傫偼巹偺僷僩儘儞乿偲怱偐傜姶幱偟偰偄偨丅 偦傟偱丄戣柤偑乽巹偺撔偝傫乿側偺偩丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  偲偙傠偱丄儔僗僩偱撍慠傝偮巕偝傫偼丄僗儁僀儞偵椃棫偭偰偟傑偆丅棟桼偼奊偺曌嫮偵峴偔偲偄偆偙偲丅 傝偮巕偝傫偼偦偆偲偆偍嬥偵偼崲偭偰偄偨偼偢偱偁傞丅偦傟偵傕偐偐傢傜偢側偤丄擔杮墌偑傑偩傑偩 崙嵺揑偵偼憡摉埨偄侾俋俈俁擭偵僗儁僀儞偵丄偦傟傕挿婜偺奊偺曌嫮偵峴偗偨偺偩傠偆丅 妋偐偵僗儁僀儞偼僼儔儞僗側偳偲斾傋傞偲暔壙偼埨偄偑旘峴婡戙傗儂僥儖戙偼偦傫側偵埨偔側偄丅 傑偟偰傗挿婜懾嵼偲側傞偲丄偦偆偲偆偺弌旓偑偐偝傓丅帠慜偵奊傪俀枃傗俁枃攧偭偨偩偗偱偼偱偒側偄偙偲偩丅 傕偟椃峴傪懕偗偨傝丄妛峑偵擖偭偨傝偲側傞偲摿暿偺弌旓傕弌偰偔傞丅 峫偊傜傟傞堦斣偺偍嬥偺弌偳偙偲偟偰偼丄 嘆堦忦埲奜偺恖偱傝偮巕偝傫偺奊傪墳墖偟偰偔傟偰偄傞棟夝偺偁傞夋彜偑偄偰奊傪憡摉偺枃悢 梐偐偭偰偔傟偰丄偐偮丄敿暘偔傜偄愭暐偄偟偰偔傟偨丅 嘇晝恊偐傜忳傝庴偗偨傝偮巕偝傫偺廧傫偱傞搚抧傪扴曐偵嬧峴偐傜偍嬥傪庁傝偨丅傕偟偔偼搚抧傪 攧偭偰偟傑偭偨丅乮暥旻傕彸戻乯 嘊堦忦偵偟偐偨側偔奊傪傑偲傑偭偨枃悢攧偭偨丅傝偮巕偝傫偝偊丄妱傝愗偭偰変枬偡傟偽偙傟偼壜擻側偙偲丅 乮偟偐偟屻偵傗傗偙偟偄偙偲偵側傞壜擻惈偑偁傞乯 埲忋俁偮偺偳傟偐偐側丠偲巚偆丅巹偩偭偨傜傕偪傠傫嘆偑儀僗僩丅嘇偼庁傝偨偍嬥傪曉偡偺偑擄偟偄偐側丄 偲傕巚偆丅搚抧傪攧偭偨偲偟偨傜偦傟偼偝偡偑偵垼偟偄側乧丄偭偰巚偆丅 嘊偼堦斣壜擻惈偑崅偄丅偟偐偟丄堦忦偑尒曉傝傪婜懸偡傞偐傕偟傟側偄偺偱偁偲偱偄傗側偙偲偑偍偙傞偐傕乧丅 傝偮巕偝傫傕偦傟偼廫暘抦偭偰偄傞偩傠偆偐傜側傞傋偔側傜旔偗偨偄偲偙傠偩偲偼巚偆偑乧丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  偟偐偟丄傑偁峫偊偰傒傟偽堦忦傕偁偺塮夋傪娤偰偄傞尷傝偱偼偦傫側偵崜偄恖娫偲傕巚偊側偄偺偱丄 堄奜偵奊昤偒偲偟偰傕偒偪傫偲峫偊偰偔傟偰丄斵彈偵杮婥偱搳帒偡傞婥帩偪偱峴摦偟偰偄傞晹暘傕 懡偄偺偐傕偟傟側偄丅 傕偟偦偆偩偲偟偨傜丄傝偮巕偝傫偵偲偭偰堦忦偼戝愗側巇帠偺僷乕僩僫乕偩丅 奊傪懕偗偰偄偔忋偱戝愗偵偟側偔偰偼偄偗側偄恖偐傕偟傟側偄丅 傑偨柧擔 |
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕 偍偽偪傖傫偺巕庣塖丂丂丂丂俁寧侾係擔乽撔師榊側擔乆乿偦偺侾俀侾 幵棾憿丄幵偮偹晇嵢偵偼巆擮側偑傜巕嫙偑偄側偄丅 傕偟丄巕嫙偑偄偨傜丄偝偔傜傗撔偼偲傜傗偱帺暘偺屘嫿偺壠傛偆偵偼 怳晳偊側偐偭偨偩傠偆丅 偍偄偪傖傫偲偍偽偪傖傫偵偼怽偟栿側偄偑撔偲偝偔傜偵偲偭偰偲傜傗偺忬嫷偼 偲偰傕岾偄偩偭偨偲偄偊傞偩傠偆丅 偦傟偱傕丄偍偄偪傖傫傗偍偽偪傖傫偨偪偵偲偭偰偼丄傗偼傝巕嫙偑 梸偟偐偭偨偺偼帠幚偩偭偨傛偆偩丅 戞侾係嶌乽撔師榊巕庣塖乿偱偺偍偽偪傖傫偺峴摦偼偦偺偙偲傪昞偟偰偄傞丅 偍偽偪傖傫偼撔偑嬨廈偐傜偍傇偭偰楢傟偰棃偨愒傫朧傪偲偰傕壜垽偑偭偰戝愗偵堢偰偰偄偨丅 愒傫朧偑偲傜傗偵傗偭偰棃偨偙偲偱丄偍偽偪傖傫偼惗偒惗偒偟偨昞忣偵側傝丄 枅擔偵僴儕偑偁傞姶偠偩偭偨丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  偍偽偪傖傫乽傛偟傛偟傛偟丄偍慜偼偳偙偵傕傗傝傖偟側偄傛丅偍偽偁偪傖傫偑丄 丂丂丂丂丂丂丂偪傖乣傫偲堢偰偰傗傞偐傜偹乿 幮挿乽偍偽偪傖傫丄偐傢偄偄偐偄丠乿 偝偔傜乽偲偭偰傕夰偄偰偄傞偺傛乿 幮挿乽側偵偟傠丄偙偺偍偽偪傖傫丄巕偳傕偑偱偒側偐偭偨傫偩偐傜側乿 偍偄偪傖傫丄偦偭偲偍偽偪傖傫傪尒傞丅 恖惗偺婡旝傪姶偠傞塀傟偨柤僔乕儞偩偭偨丅 偦偟偰丄偁傞擔丄愒傫朧偺晝恊偲嵅夑偺屇巕偺梮傝巕偑堷偒庢傝偵棃傞丅 偦偺帪偍偽偪傖傫偼丄帺暘偺偍暊傪捝傔偨巕嫙偺傛偆偵愒傫朧傪搉偟偨偔側偄婥帩偪偵 側偭偰偟傑偆偺偩偭偨丅 偱傕丄寢嬊偼媰偔媰偔搉偟偰偟傑偆丅 偦偺斢丄揤堜偐傜捿傞偟偰偄傞僈儔僈儔偑傑偩掁傝壓偑偭偰偄傞晹壆偱 栚傪弫傑偣側偑傜丄斶偟偘偵僆僔儊傪曅晅偗側偑傜媰偄偰偟傑偆偺偩偭偨丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  戞侾係嶌偼亀撔師榊巕庣塖亁偩偑丄傕偆傂偲偮偺暔岅亀偍偽偪傖傫偺巕庣塖亁偱傕偁傞丅 傑偨柧擔 |
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕 嶰嵤拑榪偲僄儊儔儖僪偺巜椫丂丂丂丂俁寧侾俁擔乽撔師榊側擔乆乿偦偺侾俀侽 撔偼丄擭拞椃曢傜偟偱丄嵿晍偺拞恎傕嬻偭傐偵嬤偄偺偱 嵿嶻偲巚傢傟傞傕偺偼側偵傕帩偭偰偄側偄丅 偲傜傗偺搚抧偼偄偢傟撔偲偝偔傜偑柤媊忋偼強桳偡傞偺偐傕偟傟側偄偑丄 撔偺偙偲偩偐傜丄偦傫側傕偺偼慡晹偝偔傜傗攷傗枮抝偵傗偭偰偟傑偆偵 堘偄側偄丅 偩偐傜丄撔偺帩偪暔偼偁偺僇僶儞偩偗偱偁傞丅 偟偐偟丄幚傪尵偆偲撔偼俀偮偺亀曮暔亁傪帩偭偰偄傞丅 偝偔傜偺尵偆傛偆側乽恖傪垽偡傞怱乿偲偄偆椶偺傕偺偼 崱夞偼墶偵抲偄偰偍偄偰丄弮悎偵嬥慘揑偵壙抣偺偁傞傕偺偱偁傞丅 嘆懪栻梣曄嶰嵤榪乮偆偪偖偡傝傛偆傊傫偝傫偝偄乯 嫗搒偱撔偵偄傠偄傠悽榖偵側偭偰撔傪婥偵擖偭偨恖娫崙曮 壛擺嶌師榊偑撔偵搚嶻戙傢傝偵偔傟偨拑榪丅 恖娫崙曮偺椡嶌偩偲偄偆偙偲偱壗昐枩傕偡傞偩傠偆丅 僞僐幮挿偼僞僶僐偺媧妅擖傟偵巊偭偰偄偨乮丱丱丟乯 攷偼丄堦墳栚偵偲傔偰乽偄偄拑榪偩側偁乧乿側傫偰偙偲尵偭偰偄偨偑丄 偝偔傜偑撔偺搚嶻偩偲尵偆偲丄乽側傫偩乧乿偲媫偵嫽枴傪柍偔偟偰偄偨丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂  丂丂丂 丂丂丂偝偔傜偼偙偺嶌昳偱丄摡寍嫵幒偵捠偭偰偄偨偑丄偦偺帪 乽壛擺嶌師榊偺嶌昳偑岲偒乿側傫偰撪梕偺偙偲尵偭偰偨偔偣偵丄 慡偔嫽枴傪帵偝側偐偭偨偺偑偪傚偭偲垼偟偄偲偙傠丅 掜巕偑庁傝偵棃偰丄傛偆傗偔杮暔偩偲傢偐傝丄偼偠傔偰儅僕儅僕偲 乽偙傟偑杮暔偺壛擺嶌師榊乧乿側傫偰欔偒側偑傜娪徿偟偰偄傞偺偑 偙傟傑偨壜徫偟偔傕垼偟偄偲偙傠丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂  丂 丂嘇僄儊儔儖僪偺巜椫 嵅搉搰偱偍悽榖偵側傝丄撔偲偺巚偄弌傪戝愗偵偟偨偐偭偨嫗偼傞傒偑丄 暿傟嵺偵帺暘偺偼傔偰偄偨巜椫傪撔偵搉偡丅 偍偽偪傖傫偼丄杮暔偠傖側偄偺丠偭偰偄偆傛偆側偙偲尵偭偰偨偗偳丄偝偔傜偼 慡偔怣梡偟傛偆偲偟側偐偭偨丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂  偱丄偙偺傛偆側崅壙側傕偺傪強桳偟偰偄偨偲偼偄偊丄傎傫傕偺偩偲傢偐偭偨偐傜偵偼丄 偒偪傫偲杮恖偺尦偵曉偟偵峴偔偺偑偝偔傜偺棫攈側偲偙傠丅 偄傢傟偺側偄夁忚側憽傝暔傗尰嬥傪庴偗庢傜側偄偺偼丄戞侾俈嶌乽梉從偗彫從偗乿偱 惵娤偺奊傪攧偭偨偍嬥偱偁傞俈枩墌傪丄傢偞傢偞帺戭傑偱婣偟偵峴偭偨偙偲偱傢偐傞偲 偄偆傕偺丅 偨傇傫乧 偝偔傜偼乽懪栻梣曄嶰嵤榪乿偼壛擺嶌師榊偵曉偟偨偲巚偆丅偩偄偨偄撔偼偙傫側傕偺偵壗偺嫽枴傕 側偄偩傠偆偟丄偙傫側暥壔堚嶻偺傛偆側傕偺帩偭偰偄偨偭偰晧扴偵側傞偩偗偩偟乧丄埖偄偵崲傞偟乧丅 嶌師榊偑庴偗庢傜側偄応崌偼丄嶌師榊備偐傝偺旤弍娰偁偨傝偵婑晅偟偨偐傕丅 僄儊儔儖僪偺巜椫偼乧擄偟偄偲偙傠乧丅偪傖偭偐傝偝偔傜偑偍弌偐偗偺帪偵偟偰偨傝偟偰乮丱丱乯 偦傟偼偦傟偱偄偄偲傕巚偆丅彮側偔偲傕嫗偼傞傒偵偲偭偰偼婌傫偱巊偭偰偔傟偨曽偑柣棙偩傠偆丅 椺偺嶰嵤拑榪偩偭偰丄偝偔傜偨偪偑寧偵壗搙偐枙拑側傫偐傪堸傓帪偵婥妝偵巊偭偨偭偰傎傫偲偆偼 偄偄偺偐傕偟傟側偄丅拑榪偲偼偦傕偦傕偦偆偄偆傕偺偩偲巚偆丅擔忢偱巊偭偰偙偦摴嬶偼惗偒傞偺偩丅 嶌師榊偼杮摉偼偦傟傪朷傫偱偄傞偙偲偼娫堘偄側偄偺偩偐傜丅 傑偨柧擔 |
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕 傆傒偝傫偺嵟屻偺椳丂丂丂丂俁寧侾俀擔乽撔師榊側擔乆乿偦偺侾1俋 戞俀俈嶌乽楺壴偺楒偺撔師榊乿偐傜媑壀廏棽偝傫偼搊応偡傞丅嵟弶偵偟偰 偡偱偵摪乆偨傞攐桪傇傝偩丅 摿偵傆傒偝傫偑偲傜傗偵嵟屻朘偹偰偒偰丄撔偺慜偱丄乽寢崶偡傞傫偱偡乿偲崘偘偨 帪丄枮抝偼巕嫙偩偐傜偲暓娫偵捛偄傗傜傟偰偟傑偆丅 偦偺帪偺偡偹偨枮抝偺僙儕僼 乽寢崶偡傞傫偱偡乧乿偼幚偵報徾怺偄僙儕僼偩偭偨丅 偍偄偪傖傫偺旝柇側儕傾僋僔儑儞傕徫偊傞丅 懯栚墴偟偼乽傑偙偲偝傫偭偰側偁偵丠乿乮丱丱丟乯 偦傟偵偟偰傕偩丅 傆傒偝傫偼悾屗撪奀偺彫搰偱撔偵巒傔偰偁偭偨帪埲棃丄撔傪婥偵擖傝丄戝嶃偱偺 暔岅偺拞偱丄撔傪抝惈偲偟偰堄幆偟偰偄傞偺偼扤偺栚偵傕暘偐傞傛偆偵墘弌偝傟偰偄傞丅 偦偟偰掜偺巰傪暦偐偝傟偰丄偳傫掙偵撍偒棊偲偝傟傞傆傒偝傫丅 偦傫側僊儕僊儕偺怱傪帩偭偰撔偺悁棷偟偰偄傞怴悽奅儂僥儖偵峴偒丄撔偺嫻偱 媰偔偺偱偁傞丅岲偒側婥傪嫋偟偨抝惈偵偟偐偙傫側偙偲偼偱偒側偄丅 偦偟偰丄撔偼偄偮傕偺傛偆偵亀椪奅揰亁偵払偟丄摝偘傞傛偆偵戝嶃傪棫偪嫀傞偺偱偁傞丅 棟桼傕枅夞偺乽帺怣偺側偝乿偲乽媷孅偝偐傜偺摝旔乿 偲偼尵偆傕偺偺丄偲傜傗偵栠偭偨撔偼偄偮傕偺僷僞乕儞偩偲偼偄偊丄怱偑傆偨偮偵堷偒楐偐傟丄 傆傒偝傫傪掹傔偒傟側偄偱偄傞丅偙偺傊傫偼偄偮傕側偑傜帟偑備偔丄忣偗側偄丅 偦偺娫偵丄傆傒偝傫偺恖惗偑寖曄偡傞丅 偐偮偰岲偒側抝惈乮撔乯偑偄偨丅偟偐偟丄撔偼摝偘偨丅 偦傟偱丄帺暘傪慜乆偐傜曠偭偰偔傟傞暿偺抝惈偵帺暘偺恖惗傪梐偗偰傒傛偆偲寛堄偟偨丅 偦偆偄偆応崌丄偐偮偰帺暘偑岲偒偩偭偨抝惈偵偦偺偙偲傪曬崘偟偵偄偔偩傠偆偐丠 偨偲偊偽丄撔偲寢崶偺栺懇傪偟偰偄偨偺偵丄僉儍儞僙儖偟偨偄偺側傜丄傕偪傠傫捈愙夛偭偰榖傪偡傞偩傠偆丅 傑偨丄戞係俉嶌偺愹偪傖傫偺傛偆偵丄枮抝偺巚偄傪妋偐傔傞偨傔偵丄嵟嬤偟偨尒崌偄偺偙偲傪揱偊偵 尵偭偨偺側傜丄偦偆偄偆彈偛偙傠偼傢偐傞丅枮抝偵偦傫側尒崌偄偺榖偼抐偭偰丄帺暘偲寢崶偟偰梸偟偄 偲丄尵傢傟偨偄乧丅偮傑傝枮抝偵垽傪崘敀偟偰梸偟偄丅偲偄偆偙偲偩傠偆丅 偟偐偟丄傆傒偝傫偺応崌偼傑偭偨偔尒摉偑偮偐側偄丅 傕偟丄傆傒偝傫偑撔偺偙偲傪抝惈偲偟偰岲偒偱側偔丄恊愗側壎恖偲偩偗偟偐巚偭偰偄側偗傟偽丄 偡傋偰偺捯咫偑崌偆丅偟偐偟傆傒偝傫偼撔偵懳偟偰抝惈傪堄幆偟偰偄偨偲巹偼巚偆丅偦偆偱側偄偲 抝惈偺晹壆偵棃偰偦偺旼偱怮傛偆側傫偰偟側偄丅廫敧偺弮忣柡偱偼側偄偺偩偐傜丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  偦偆側傞偲丄寢崶傪寛堄偟偨傆傒偝傫偼側偤撔偺尦偵曬崘偵偒偨偺偩傠偆偐乧丅 朰傟側憪偺儕儕乕偑儔僗僩偱寢崶偟偨帪丄撔偵偦傫側曬崘偼偟偰偄側偄丅僴僈僉侾杮偦偭偲弌偟偨偩偗丅 傑偩楒怱偑偁傟偽偁傞傎偳夛偆偲怱偑梙傜偖偼偢丅 撔偼尵偆乽傢偞傢偞棃傞偙偲側偐偭偨傫偩傛丄偙傫側偲偙傑偱乧丅僴僈僉侾杮偩偟傖偡傓偙偲 丂丂丂丂丂丂偠傖側偄偐丅偙偭偪偺婥帩偪偵傕側偭偰偔傟偭偰尵偆傫偩傛丅偙傫側嶴傔側婥暘偵 丂丂丂丂丂丂偝偣傜傟偰傛乧乿 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  傂傚偭偲偟偰丄傆傒偝傫偼傑偝偐帺暘偑偦傫側偵崨傟傜傟偰偄傞偲偼巚偭偰偄側偐偭偨偺偐傕偟傟側偄丅 傕偟偐偟偨傜丄傆傒偝傫偼撔偑帺暘偺偙偲側傫偐岲偒偱側偄偲巚偭偰偄偨偺偐傕偟傟側偄丅 壜垼憐側帺暘傪恊恎偵側偭偰庤揱偭偰偔傟偨偑丄帺暘偺偙偲偼桭恖偲偟偐巚偭偰偄側偐偭偨丅 偩偐傜偙偦偁偺栭丄帺暘傪堦恖晹壆偵巆偟偰撔偼嫀偭偰偟傑偭偨偺偩乧丄偲丅帺暘偼岲偒偩偭偨偗偳乧丅 偦偆偩偲偡傟偽丄偲傜傗偵曬崘偵偒偨堄枴偑彮偟偼傢偐傞乧傛偆側婥偑偟側偄偱傕側偄丅偱傕傗偭傁傝 傢偐傜側偄偐側乧乮丱丱丟乯丅 偦偟偰偁偺儔僗僩偺懳攏偱偺傆傒偝傫偺椳偼側傫側偺偩傠偆丅 偁偺椳偼杮摉偵怱偐傜岲偒偩偭偨抝惈偵尒偣偨嵟屻偺椳偩偭偨偲巚偄偨偄丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  傑偨柧擔 |
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕 恴朘壠偲崟斅壠丂丂丂丂俁寧侾1擔乽撔師榊側擔乆乿偦偺侾18 嶐擔媣偟傇傝偵亀塀偟寱婼偺捾亁傪尒偨丅僶儕搰側偺偱傕偪傠傫塮夋娰偱側偔DVD丅 懅巕偑尒偰偄偨偺偱僠儔僠儔偭偲巹傕尒偰偟傑偭偨丅 朻摢偵嬤偄僔乕儞偱攞徿愮宐巕偝傫偲媑壀廏棽偝傫偑塱悾偝傫丄徏偝傫丄 揷敤偝傫偨偪偲堦弿偵埻楩棤傪埻傫偱戝徫偄偡傞僔乕儞偑偁傞偺偩偑丄 巹偼偁偺僔乕儞偑戝岲偒側偺偩丅 棟桼偼扨弮丅攞徿偝傫偲媑壀偝傫偑摨偠応強偱怘帠傪偟側偑傜夛榖偟偰偄傞偐傜偩丅 偝偔傜偲枮抝傪巚偄弌偟丄墦偔偼亀梱偐側傞嶳偺屇傃惡亁偺柉巕偲晲巙傪巚偄弌偟偰偟傑偆丅 壗擔偐慜偵傕彂偄偨偑丄媑壀廏棽偝傫偵偼擇偮偺戝壨偑棳傟偰偄偰丄堦偮偑乽抝偼偮傜偄傛乿偱丄 傕偆堦偮偑乽杒偺崙偐傜乿偩丅擇偮嫟偵彮擭婜偐傜寢崶傑偱斵偺恖惗偲摨帪恑峴偱暔岅偑恑傫偱 偄偭偨偺偩丅 偩偐傜媑壀廏棽偝傫偵偼幚嵺偺偛椉恊埲奜偵丄偁偲擇慻椉恊偑偄傞丅 亀恴朘丂攷丄偝偔傜丂亁偲丂亀崟斅丂屲榊丄椷巕亁偩丅 偱丄偛懚抦偺捠傝乽抝偼偮傜偄傛乿偱傕側傫偲屲榊偝傫傗椷巕偝傫偲 嫟墘偟偰偄傞偺偩丅 戞俀俋嶌乽撔師榊偁偠偝偄偺楒乿偱巰傫偩偼偢偺偍曣偝傫偺 崟斅椷巕偝傫偲偁偠偝偄帥偱丄嵞夛偟偰偄傞乮丱丱丟乯 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  偍晝偝傫偺崟斅屲榊偝傫偲偼戞係俉嶌乽撔師榊峠偺壴乿偱墏旤戝搰偱嵞夛偟偰偄傞丅 傕偭偲傕偍晝偝傫偐傜斵偑帺嶦偡傞傫偠傖側偄偐偲偢偭偲寈夲偝傟偰偼偄偨偑乮丱丱丟乯 偙偺嵞夛偺屻傕傑偩傑偩弮偲屲榊偝傫偲偺僪儔儅偼俀侽侽俀擭傑偱懕偄偰偄偔丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  偦偺懠丄拞敤偺偍偠偝傫丄愥巕偍偽偝傫丄峀夘丄傾僀僐丄偁偨傝偲傕媑壀偝傫偼 乽抝偼偮傜偄傛乿偺拞偱嵞夛偟偰偄傞偺偱偁傞丅 偦偺搙偵巹偼僯儎僯儎偟偰偄傞丅 幚偼乧丄側偵傪塀偦偆巹偼乽杒偺崙偐傜乿偺戝僼傽儞側偺偱偁傞丅乽杒偺崙偐傜乿偼 乽抝偼偮傜偄傛乿摨條丄尒偨恖偺岲偒寵偄偑寖偟偄僪儔儅側偺偱丄側偐側偐恏偄傕偺偑 偁傞偑丄偄偄傕偺偼偄偄偺偩偲怱偐傜僉僢僷儕巚偭偰偄傞丅 偙偺乽杒偺崙偐傜乿傕嶐擔偺巹偺堄尒捠傝偄偊偽丄挿偄挿偄侾杮偺僪儔儅偲尵偊傞偩傠偆丅 幚偵尒偛偨偊偺偁傞寠偺側偄僪儔儅偩偭偨丅僥儗價僪儔儅偺惼庛偝偼偙偙偵偼側偄丅 偟偐偟僥儗價側傜偱偼偺僗僇僢偲偟偨僥儞億偺偄偄僼僢僩儚乕僋晹暘傪偒偪傫偲堄幆偟偰偄傞偺偑 偝偡偑偩側偭偰巚偆偺偩丅 傑偨柧擔 |
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕 媑揷擔弌巕偝傫偺巚偭偨偙偲丂丂丂丂俁寧侾侽擔乽撔師榊側擔乆乿偦偺侾1俈 偙偺僔儕乕僘傕戞40嶌傪墇偊傞偁偨傝偐傜師戞偵埈旤偝傫偺懱挷偑偡偖傟側偔側傝丄暯峴偟偰 儅僪儞僫偲偺暔岅偑庛偔側偭偰偄偔丅摿偵偦傟偑尠挊偵尰傟傞偺偑戞42嶌丄戞43嶌丄戞44嶌丄 偁偨傝偩丅偙偺3嶌偵娭偟偰偼儅僪儞僫晄嵼偺姶偑庒姳偁傞丅 偦偺戙傢傝偵丄庒偄枮抝偲愹偪傖傫偺惵弔偺暔岅偑巒傑偭偰偄偔偺偱偁傞丅 偟偐偟丄埲慜傕彂偄偨偲偍傝丄偦傟偱傕傗偼傝枮抝偲愹偪傖傫偼僒僽偱偁偭偰傗偼傝撔偲儅僪儞僫偺 垼偟偄楒偺暔岅偑偙偺僔儕乕僘偺妀側偺偼尵偆傑偱傕側偄丅 枮抝偲愹偪傖傫偱偼庒偄娤媞偑擖傞偐傕偟傟側偄偑丄偦傟偱偼嶌昳懌傝摼側偄偺偱偁傞丅 摿偵戞44嶌乽撔師榊偺崘敀乿偼偁偺媑揷擔弌巕偝傫偲偄偆婬桳偺栶幰嵃傪帩偭偨攐桪傪 婲梡偟側偑傜傕丄斵彈傪廫暘偵偼惗偐偟偒傟偰偄側偐偭偨丅 偙傫側傕偭偨偄側偄偙偲偼側偄丅偁偺恖偑曻偮僆乕儔偼丄椙幙偺暔岅偺拞偱偝偧偐偟婸偒傪 曻偮偙偲偼懠偺嶌昳偺墘媄傪尒偰偄傟偽暘偐傞丅 斵彈偼帺暘偺僄僢僙僀偺拞偱偙偺帪偺弌墘偺偙偲傪偙偆彂偄偰偄傞丅 亀戜杮傪撉傫偱傕偙偺惞巕偝傫偲偄偆偺偼偳偆偄偆恖偐偤傫偤傫暘偐傜側偄丅 乽撔偝傫乿偺戜杮偭偰丄嶳揷梞師偝傫偺摢偺拞偵偁傞傕偺傪彂偄偰偁傞偩偗偩偐傜丄壗捠傝偵傕 撉傔傞傫偩偗偳丄偳偆偟偨傜堦斣偄偄偺偐偑傢偐傜側偄丅 乽偩偭偨傜傑偢丄娔撀偺榖傪暦偄偰傒傛偆乿暦偒偵峴偭偨丅榖傪偟偰丄偦傟偱傕暘偐傜側偄亁 寢嬊丄媑揷擔弌巕偝傫偼弌墘偟丄塮夋晻愗傝偺帪偵塮夋娰偵娤偵峴偔丅偦偟偰帺暘偺棈傒偺晹暘偵 暔懌傝側偝傪姶偠丄乽偆乕傫丄偮傑傜側偐偭偨乿偲尵偭偰偟傑偆偺偱偁傞丅 偦偟偰偙偆傕尵偆 乽崱偼愄偺撔偝傫偲堘偭偰丄嶌昳偺拞偵榖偑2偮偔傜偄偟偐側偔偰丄偦傟傕偲偭偰偮偗偨傛偆側榖偩偐傜丄 撔偝傫傑偱偲偭偰偮偗偨傛偆側恖偵側偭偪傖偆丅偙傟偠傖丄幣嫃偑偱偒側偄偩傠偆側偁乧丄偲傢偨偟側傫偐偼 巚偆傫偩偗偳丄偱傕埈旤偝傫偼戜杮偵慺捈偵傗偭偪傖偆偱偟傚丅晄巚媍偩側偁丄偳偆偟偰傕偭偲 傗偭偪傖傢側偄傫偩傠偆偲巚偭偨丅乧乧 偱傕埈旤偝傫偼庤傪敳偄偰傞傫偠傖側偄偺傛丅偁傫側偵塮夋偺偙偲傪傛偔暘偐偭偰偄傞恖偑戜杮偵拲暥傪 偮偗偨傝偟側偄偱戝偒側棳傟偵恎傪擟偣偰傗偭偰偄偔丅 偦傟傕傑偨奿岲偄偄側偁偭偰乧乿 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  攞徿偝傫偑丄偐偮偰尵偭偰偄偨傛偆偵埈旤偝傫偼挿偄挿偄堦杮偺塮夋偵弌墘偟懕偗偰偄傞偺偩傠偆丅 偦傟備偊戝偒側棳傟偺側偐偺崱偼傕偆嵟屻偺惷偐側備偭偨傝偲偟偨堄幆偺拞偱嶳揷娔撀傪怣偠側偑傜 帺暘偺懱挷偺撪偱弌棃偆傞偙偲傪弆乆偲墘偠偰偄偨偺偐傕偟傟側偄丅 巹偼嶐擔傕彂偄偨偑丄弶婜偺丄偮傑傝惵弔婜偺乽抝偼偮傜偄傛乿偲廫嶌戜偺憇擭婜偺廰偔偰慺揋側 乽抝偼偮傜偄傛乿偲偑戝岲偒偩丅傂偲偮傂偲偮偺嶌昳傪偦傟偧傟壗廫夞偲尒偰偄傞偲巚偆偑丄屻敿偺朿戝側 検偺榁擭婜偺乽抝偼偮傜偄傛乿傕偐側傝岲偒偱丄尒傞夞悢偼幚偼偦傫側偵曄傢傜側偄偺偱偁傞丅 偦傟偼丄攞徿偝傫傗媑揷擔弌巕偝傫偑尵偆傛偆偵丄戝偒側棳傟偺拞偺備偭偨傝偲偟偨挿偄墿崹偵恎傪擟偣 側偑傜丄孞傝曉偟扺偄楒傪偟偰備偔撔偑傗偼傝廰偔丄奿岲偄偄偐傜側偺偩偲巚偆丅 偙偺僔儕乕僘偼偙偺傛偆側尒曽偑嫋偝傟傞悢彮側偄塮夋偩偲巹偼巚偭偰偄傞丅塮夋昡榑壠偺傒側偝傫偼 偙偺傛偆側尒曽偼嫋偝傟傞偼偢傕側偄丅1嶌昳侾嶌昳傪偟偭偐傝斸昡偟側偔偰偼側傜側偄丅巇帠偩偐傜偱偁傞丅 巹偼堦僼傽儞偩偐傜偙偺尒曽偑嫋偝傟傞丅 乽抝偼偮傜偄傛乿偼偨偭偨堦杮偺挿偄挿偄塮夋偱偁傞丅偦傟備偊恖娫偲摨偠偔偦偺棳傟偺拞偱惵弔婜偑偁傝丄 憇擭婜偑偁傝丄偦偟偰嵟傕帪娫揑偵偼挿偄榁擭婜偺墿崹偑偁傞偺偩丅 恖惗偼楌巎偱偁傝丄僩乕僞儖偱偁傞偺偲摨偠偔丄偙偺僔儕乕僘偺斢擭傕堦尒丄偦偙偩偗傪尒傞偲丄偨偩巭傑偭偰 偄傞傛偆偵尒偊偰傕丄戝偒側棳傟偺側偐偱尒傞偲備偭偔傝偲棳傟偰偄偔偺偑尒偊傞丅 偦偆偩偐傜偙偦丄偁偺堦尒惓帇偱偒側偄傛偆側斶偟偄埈旤偝傫偑搊応偡傞嵟屻偺戞48嶌偑丄戝偒側棳傟偺拞偱丄 戝偒側岝偵曪傑傟偰惷偐偵扺偔婸偒巒傔傞偺偩傠偆丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  傑偨柧擔 |
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕 惵弔婜偺亀抝偼偮傜偄傛亁丂丂丂丂俁寧俋擔乽撔師榊側擔乆乿偦偺侾1俇 戞侾嶌乽抝偼偮傜偄傛乿偲戞俆嶌乽朷嫿曆乿偼偁傞嫟捠揰偑偁傞丅 嶳揷娔撀傕埈旤偝傫傕弮悎偵偙傟偱乽抝偼偮傜偄傛乿偼嵟屻偐傕偟傟側偄 偲巚偭偰偄傞揰偩丅 偦傟偵懳偟偰丄戞俇嶌乽弮忣曆乿傗戞俉嶌乽撔師榊楒壧乿偼偙傟偐傜僔儕乕僘壔 傪恾傞偲偄偆婥峔偊偺傕偲偵枹棃傪尒悩偊偰戝妡偐傝偱嶌偭偰偄傞偺偑傛偔暘偐傞丅 偳偙偐偟傜庤寴偔丄姶摦応強傪偐側傝堄幆偟偨傛偆偵傕尒偊側偔傕側偄丅傕偪傠傫偩偐傜偙偦 埨掕姶偑偁傝丄暔岅揑偵傕廩幚偟丄埨怱偟偰傒偰偄傜傟傞偲偼偄偊傞偺偩偑丅 撔帺懱傕戞俇嶌埲崀彊乆偵僗儅乕僩偵昤偐傟偰偄傞丅 僉儍僗僩偺柺偵偍偄偰傕丄戞俇嶌偱偼庒旜暥巕丄怷斏媣栱丄 戞俉嶌偱傕抮撪弤巕丄戞俋嶌偱偼媑塱彫昐崌偲憡摉崑壺側婄傇傟偩丅傕偪傠傫徏抾偺愰揱偺 巇曽傕曄傢偭偰峴偔丅 偦偆偄偆堄枴偱偼戝憶偓埲慜丄偮傑傝亀栭柧偗慜亁偺戞侾嶌偲戞俆嶌偺傒偢傒偢偟偝偼戝曄側傕偺偩丅 慜偵傕彂偄偨偑丄戞侾嶌偼丄偙傟偑嵟弶偱嵟屻偺塮夋壔偩偲娫堘偄側偔慡堳巚偭偰偄偨丅惂嶌帺懱偑 婋傇傑傟傞傎偳丄夛幮懁傕僊儕僊儕偺彸戻偩偭偨丅偦傟備偊偄傠傫側榖傪惙傝偩偔偝傫偵偟丄偟偐偟偦傟偑 幚偵僥儞億椙偔僄僱儖僊僢僔儏偵塣傫偱偄偔偺偱偁傞丅憐偄偑慡偰堦揰偵崬傔傜傟偰偄傞偐傜側偺偩丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  戞俆嶌傕慜敿偱戞侾嶌偺偁偺妶婥偲僥儞億偑慼傝丄屻敿偱偼摉帪傑偩嫏巘挰偩偭偨塝埨傪晳戜偵丄 嶳揷娔撀偼丄傑傞偱崱傑偱偺婥帩偪偺惍棟傪偡傞傛偆偵僥儗價僪儔儅偺亀抝偼偮傜偄傛亁偺僉儍僗僩偨偪傪 巊偭偰丄傕偆堦偮偺撔偺怱偺抲偒強傪嶌偭偰偄傞丅偦偙偵嶳揷娔撀偺梋寁側婥晧偄偼姶偠傜傟側偄丅 堦婜堦夛偺廤拞椡偝偊姶偠傜傟傞丅 偙偺偁偨傝偺帪婜偼懠偺嶌昳偲惂嶌偑僟僽偭偰偄傞偺偱偲偰傕憗偔儚乕僢偭偲嶌偭偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄 嶨側墘弌偼側偄丅傛傎偳僗僞僢僼丄僉儍僗僩偲傕偵婥椡偑廩幚偟偰偄偨偺偱偁傠偆丅傒傫側暣傟傕側偔惵弔偩偭偨偺偩丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  偙偺傛偆偵戞侾嶌摨條丄偙偺戞俆嶌偼嵟傕乽抝偼偮傜偄傛乿傜偟偄嶌昳偵側傝偊偰偄傞丅惵弔婜偺嶳揷梞師丄 埈旤惔偺嵟屻偺弮悎側僉儔儊僉偑偁偭偨傛偆偵傕巚偊傞丅僔儕乕僘壔偑偳偆偺丄崙柉揑恖婥傪妉摼偡傞偐 偳偆偐乧側傫偰偙偲傪傑偩峫偊偢偵惂嶌偱偒偨婬桳偺帪婜偩偭偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅 偦傟傜偺娫偵偁傞嶌昳丄戞俀嶌乽懕抝偼偮傜偄傛乿傕媟杮傪僥儗價斉偐傜偐側傝攓庁偟偨偲偼尵偊丄枾搙偺擹偄丄 婲彸揮寢偺偟偭偐傝偟偨摦偒偺偁傞嶌昳偵巇忋偑偭偰偄傞丅 師偺戞俁嶌乽僼乕僥儞偺撔乿傕丄埈旤惔偲偄偆攐桪偺傕偆堦偮偺婄傪晜偒挙傝偵偡傞惗乆偟偄墘弌偱 怷嶈搶娔撀偺怱堄婥偑巉偊傞偙傟傑偨弮悎側婸偄偨嶌昳偱偁傞丅 戞係嶌乽怴抝偼偮傜偄傛乿傕僥儗價斉偺帩偭偰偄偨壓挰忣弿揑側丄壏偐偄恖娫柾條偑孞傝峀偘傜傟丄 徏抾姴晹懁偺掅梊嶼抁婜娫惂嶌巜帵偺偒偮偄僴儞僨傪忔傝墇偊偰亀抝偼偮傜偄傛偺尨揰亁偲傕偄偊傞嬻婥傪 懚暘偵昚傢偣偰偄偨丅僥儗價斉偵怺偔実偭偰偒偨彫椦弐堦娔撀側傜偱偼偺丄枴傢偄怺偄壚嶌偵側偭偰偄傞丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  偦偆偄偆堄枴偱偼丄帪娫傕梊嶼傕側偔戝朲偟偩偭偨偲偼偄偊丄僗僞僢僼傕僉儍僗僩傕傕偭偲傕擱偊丄嵟傕弮悎偵 塮夋嶌傝偵杤摢偟偨偺偑挻抁婜娫偱嶌偭偨偙偺俆嶌昳偲傕偄偊傞丅 偙偺俆嶌昳傪尒偰偄傞偲丄傛偦備偒偺忋拝傪拝傞慜偺愒棁乆側僟儃僔儍僣偲僗僥僥僐巔偺撔偑栚傪僊儔僊儔偝偣偰 僗僋儕乕儞偐傜旘傃弌偟偰偒偦偆偩丅 戞俉嶌乽撔師榊楒壧乿埲崀戞侾俉嶌乽撔師榊弮忣帊廤乿傑偱偺偺惉弉偟偨僗儅乕僩側戝寙嶌孮傪尒偰偄傞偲憇擭婜偺戝恖偺 枺椡偵堨傟偰偄偰儂儗儃儗偡傞偑丄惵弔婜偲偄偆傕偺偼偦傟偲偼暿偵丄偐偗偑偊偺側偄悷傫偩婸偒偵枮偪堨傟丄偦傟偼 偄偮傑偱傕峥偟偔偄偲偍偟偄傕偺側偺偩丅 傑偨柧擔 |
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕
嵟怴偺僐儔儉偼偙偪傜 |
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕
|
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕
|
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
|
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
|
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
|
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
|
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亀撔師榊側擔乆亁僶僢僋僫儞僶乕丂丂丂丂丂丂丂丂丂
|